温知会について
会長挨拶
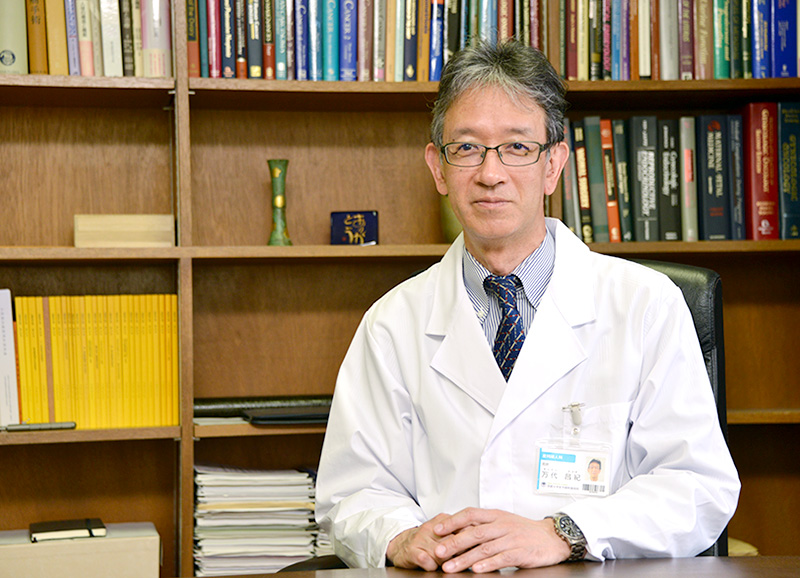
温知会の先生方、こんにちは。このたび、温知会のホームページを新たに立ち上げました。その最大の目的は、会員のみなさま相互の情報交換の場を作ることです。
温知会はご存知のように京都大学婦人科学産科学教室の同窓会として、400名あまりの会員から成り立っています。同窓会の役割はさまざまあります。これまでの歴史のなかで教室で大きな行事があるごとに温知会には財政面を含めて強力なバックアップをいただいてきました。使わなかった資金はその後の温知会の屋台骨を支えてきました。
また、毎年の「教室を励ます会」へのご寄付は昨今の厳しい事情の中でリクルートや教室関係にありがたく使わせていただいております。このように温知会はこれまで教室の「応援団」として大変ありがたい存在でした。しかしながら、一方的に教室を応援するだけでは同窓会としての存在感が薄くなってしまいます。そのため、夏のサマースクール・冬の総会・現地総会等の機会を設けて、会員相互が顔を合わせ情報交換ができる場を作るべく努めて参りました。このような機会に、若い先生方にどのようにしたら出席してもらえるか、は実はもう20年も前からあれこれと議論して努力してきたことです。
組織に属する形、というのは難しいものです。特に温知会は親睦組織、であり、強制して帰属意識を喚起する、という性格のものではありません。一方で温知会の代表として、私自身は会員の先生が温知会の一員である、という意識を「気持ちよく」持っていただきたい、と切に願っています。「温知会が何をしてくれるかを問うな、何ができるかを問え」などどは決して言いませんが、「温知会が自分たち会員のためにできることって何だろう」「温知会をどのように使えば会員みんなの役に立つだろう」という主体的な関りはぜひ、求めたいと思います。会員の会員による会員のための組織であることが存続のために必要な要件です。
昨年から始めた「KAMOGAWA study」はそのひとつの試みです。日頃、臨床をしていて疑問に思う課題を持ち寄って、温知会関連病院全体で臨床研究をおこなって、その答えを出す仕組みを作りたい。それによって関連病院発の横断的なリサーチを複数立ち上げ、大学以外でもリサーチの経験が積めるような仕組みを作りたい、というのが私の意図です。「温知会サイバーチーム」というのも作ってみました。未来対応型の人材育成の核にしたいと思っています。研究以外でも、各々の会員がキャリアアップ・自己実現のための資金を必要とする場合に、それを奨学金のような仕組みで出せないか、というようなことも考えつつあります。働き方の問題、女性医師の問題も、会員みんなでコンセンサスを作って解決していくような仕組みを作れればと思います。大学や教室はこれからますますオープンな性格になって行きますが、その分、いろんなことを各関連病院や個人で解決しなければならないことが増えてくると思います。そのなかで温知会が会員相互の横のつながりを通じて問題解決、キャリアアップの器となることを期待します。ぜひ、多くの知恵をいただけますようよろしくお願いいたします。
温知会会長
万代昌紀